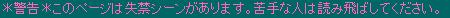
愕然とした。同じコネ入社でも自分とは比較にならないハードさだった。
これまで僕は、自分の人生をずっと呪っていた。運の悪い奴だという思いは、今でも変わりがないが、変わろうと思えばいつだって変われた筈だ。だがそうしなかったし、そういう技量もなければ努力しなかったと今でも思う。だが、あのとき自分が助けた金持ちのユウタも、けっして恵まれた人生ではなかったのだ。生まれる前から家族に翻弄され、今も自分で選択できる立場にはない……。
彼の人生を僕が評価することなどできはしないが、勇太の前で万が一にでも僕が、コネ入社の事実に負い目を感じることなどあってはならないのだと、僕は思う。
「俺だってコネでこの会社に入りました。それも社長の一存で受け入れられた立場です。……いずれ俺はここで、幹部として会社を支える側に立つのでしょう。今のところ、兄と俺、どちらが父の後継となるかは、まだまだわからないですが……。もちろんそれを断ることだってできたわけですし、選んだのは自分です。けれど、まだ1度しか給料をもらっておらず、大学時代のアルバイトの貯金も、日々の生活と医療費で使い尽くした俺に、それを断る勇気なんてありません。……リョウちゃん、自分で思い通りの人生を生きている人なんて、どれほどいると思いますか?」
少なくとも。
「それは……」
口を開いて、僕はそのまま何も言えなくなった。だが、少なくとも、目の前にいるこの男より、僕はいくらか自分の生き方を変えられる余地があった筈だ……それは間違いないような気がした。僕はその努力を放棄し続けただけのことだ。
「俺は今、父の元にいる。……幸い義母が嫌がってくれたお蔭で、一人暮らしは許されてますけどね。それでも、自分が社内で人目を……けっしていい意味ではなく引いている自覚もあります。けれど、それを甘んじて受け入れ続けるしかない。出来る限りのことをやって、周りを見返す……そして自分の居場所をなんとしても死守する……そうしないと、今すぐにでも死んでしまいそうな人達がいて、愛する彼らを俺は見捨てることができないから」
「……」
なんでも器用にこなすように見える狼森も、死に物狂いであがき続け、人一倍の努力をしていた……だからこそ今の狼森がいる……考えてみれば当然のことだ。自分は……今まで一体何をして、どれだけのことを成し遂げたというのだろう。この男の前では、それを思い返すのも恥ずかしいと思った。
「けれどね。……自分の置かれた現実を嘆いたって仕方がないし、こんなこと、リョウちゃん以外に打ち明けるつもりもない。だって、俺は京都にいる家族を除けば、リョウちゃん以外どうだっていいし、何を言われても平気だから……」
「お前……」
なんだかこそばゆくて仕方がなかった。そして初めて、目の前の男が愛しいと、本気で思った。
「リョウちゃんにはリョウちゃんの人生があって、リョウちゃんの苦しみがある……俺はそれを否定しないし、それでいいと思う。そんなリョウちゃんが好きだから……」
「よせよ……」
深く考えもせずに照れて俯くと、狼森は構わずに畳みかけた。
「もっと苛められて、苦しんで、泣いてぐちゃぐちゃになってほしい……リョウちゃんが藻掻きあがく姿は最高にゾクゾクするから……本当はそんな姿を俺はひとり占めしたい。けど、大勢の前で罵倒されて、顔を真っ赤にしながら何も言えなくなっているリョウちゃんも捨てがたい……」
「お前、一体何言って……」
狼森は目をキラキラと輝かせながら僕を見つめ……だが、おそらくその目に現実の僕は、もはや映っていないような気がした。スーツに隠されているパンツの前はこんもりと膨らんでさえいる……ここはまだ会社のエレベーターホールだというのに。
そういえばボタンを押していなかったと思い、僕はパネルに近付こうとしたが。
「お、おい……お前何し……」
背後から伸びた長い腕が、湧きの下から入り込んで、ダイレクトに僕の股間を掴んでいた……そのまま撫でまわされる。
「やっぱり……リョウちゃんのは俺より小ぶりだからわかりにくいけど、ずっと勃ててましたよね。知ってたんですよ」
「や、やめ……放せって……」
大きな掌が僕のものを鷲掴んで擦りあげ、親指でグリグリと先端を押し潰される……じんわりと下着に沁みて張り付いている感覚があった。このまま続けられては、いずれ外側にまで響いてくる……今日のスーツは灰色なので、濡れたら丸わかりだ。焦って身体を捻ろうとするが、もう片方の長い腕が、僕の腹を押さえて放そうとしない。身を捩りながら抵抗を続けていると、すっとその手が上を目指し、今度はジャケットの上から胸を揉まれる。我知れず口を開いて仰け反り、狼森の男らしくて固い胸板へ頭を押し付けた。
「ほら……リョウちゃんの放せは、もっとしてって意味で間違いなかった……すっかり勃起してますね。こっちも乳首の感触が、分厚いジャケットの上からでもわかりますよ……気持ちいいんでしょ」
「や……やだ……こんなとこ、誰かに見られたら……」
ここは会社だ。セキュリティーゲートで守られていない場所は、当然ながら監視カメラだらけで、リアルタイムで警備室に映像が送られ続けている。エレベーターホールもプライバシーの埒外である。今この瞬間も、狼森が僕に何をしているのか、そして僕がどんな顔をして乱れているのか……もしもモニターを見ていたら警備員達に知られているのだ。それも落ち着かないが、セキュリティーゲートになっている自動ドアが開き、残って仕事をしている同僚が、中から出て来ないとも限らないのである。たとえば……。
「今、何を考えました……? リョウちゃんのコレ、ビクビク跳ねましたよ……とうとうスーツも汚れちゃいましたね。一体誰に見られることを想像したんです?」
「ち、ちがっ……僕はただ、中にまだ鹿橋さんがいるって思って……い、いやっ、そんな強いっ……」
鹿橋の名前を出した途端、狼森は僕のペニスを力いっぱい握り締めた。その強烈さに僕は身体が竦み、視界に涙が滲む。
「聞き捨てならない発言ですね。鹿橋さんのことを考えて、リョウちゃんはエレベーターホールでイッちゃったわけだ」
侮蔑するように言いながらも、狼森は手の力を緩めようとしない。左手はジャケットの中へ入り、ドレスシャツの上から乱暴に乳首を捻ったり、引っ掻いたりしている。放出の快感と、敏感になった乳首に対する痛いほどの刺激、そして性器への圧力で、僕は頭が可笑しくなりそうだった。
「最近、あの人やたらとリョウちゃんに優しくなりましたよね。ねえ、実はあの人、リョウちゃんに気があるんじゃないですか? 俺が見ていないところで一体何を言い寄っているのやら……そういえば先週、俺が新人合宿から戻ってきたとき、呼んでもリョウちゃんうちに来なかったよねえ。そして次の日は、3回も風呂場でお漏らししてたし」
「ば、馬鹿っやめろって……会社で何言って……」
セックスのプレイを話題にされて、僕は大いに焦った。
「否定しないんですね。実はもう鹿橋さんにヤらせてるんじゃないでしょうね」
「そんなわけないだろっ……あの人はただ、お前が僕にきつく当たるから、心配して……や、やめろ……それ、ダメ………んあああああああああああああああっ」
狼森はそのままスーツの上から、手の内の物を一気に擦りあげ、僕は立て続けにイかされた……ただでさえ先走りで濡れていた下半身は、暴発で下着がダメになり、灰色のパンツの前が、言い訳できないほど股間に沁みを作ってしまった……その沁みがどんどん広がり足元まで濡れていく。僕はいつにない開放感に身体をビクビクと跳ねさせながら浸っていた。
「こんなところでおしっこまで漏らすなんて……大人失格ですね」
スーツのパンツが股間から下までびしょぬれだった。これでは電車どころかタクシーにも乗れない。
「酷い……お前、酷すぎだろ……」
そういえば、帰る前にトイレへ寄って行くつもりだった……そんなことをぼんやりと考えたが、何もかも後の祭りだった。視界が徐々に揺らめいて、頬を次々と伝っていく。二人分の革靴の下で水溜りが広がって、カーペットの色を変えつつ辺りにアンモニア臭が立ち込めた。
「気持ち良かったくせに、素直になりなさい……どうせあなたは、こんなものじゃあ足りないでしょう。けれど、さすがにこれ以上やったら、警備員が飛んできますからね……移動しましょう」
そういうと、狼森は僕を連れてトイレへ移動した。
05