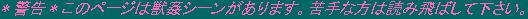
「おおっ、こいつは名器だ……兄ちゃんのいいなあ…」
僕が射精しても中に息づいていた男はそんなことを言いながら、まだ硬さを保っている勃起をしつこく擦り付ける。立て続けに犯されて、すっかり広がっていたであろうその場所は、性感を極めたあとでは、もはや痛みよりも快感のほうが勝っていた。
「ああっ、……いいっ、いいっ……んはあっ」
喘ぎ声しか出てこない口を、また誰かに犯される。彼らの中で犯され役の男も、また別の男のものを受け入れながら、違う男のペニスを銜えていたようだ。
どこかで犬の鳴き声が聞こえていた。
その後、何度尻と口を犯されたのかは覚えていない。そのたびに上と下から精液を流し込まれ、身体中に浮浪者達の体臭を移されて、僕の身体もすっかり不衛生を極めていた。
「ああっ……やぁ……」
もう何回目か分からない薄い精液を出したところで、頭上に荒い息遣いを感じる。
ハッハッ…!
軽い足取りと地面を爪で引っかくような音で、先ほど近くにいた野良犬が、傍までやってきたことを理解した。
「何……えっ」
疲労困憊の身体を無理やり起こされ半回転させられると、その場に跪くように誘導される……やってきた犬と対峙するような角度だ。とたんに目に飛び込んできたものにギョッとする。
「兄ちゃん、今度はコイツをよくしてやんな」
最初に僕を覗き込んでいた男が、耳打ちするように言って、僕の頭を押さえつけた……目の前には真っ赤な肉塊……大きく勃起した犬の性器だ。なぜかこの犬は、僕らの狂った宴を見て興奮していたのだ。
動物のつるりとした性器が唇に当たる……ハッハッという息遣いとともに、生暖かい雫がボタボタと頭や肩に落ちてきた。思わず口を開く。すると、誰かが再び僕の頭を押さえつけて、あっという間に僕は犬の性器を銜えていた。その後は一心不乱に犬のペニスを嘗め回した。まもなく僕は再び地面に両手を突くと、今度は犬に尻を向けて待ちわびた。すっかり興奮していた僕は、圧し掛かる獣の体重と暖かい体温、滑らかな肌触りを感じ、意外とスムーズに入ってきたペニスに再び性感を刺激される。
ハッハッハッ……。
しなやかな身体が背中に乗って、長く細い足が尻を跨ぎ、もどかしそうに宙を掻き続ける。
「ああっ……すごいっ…出てるっ……」
犬の行為は想像を遥かに超えていた。いきなり始まった射精は人間のものよりずっと多く、猛スピードで腰を打ちつけながら、同時に犬は僕の中へと子種を送り続けていた。ただでさえ何人もの浮浪者の精液でいっぱいになっていた僕の腹は、あっというまにいっぱいになり、それでもなお大量の獣の子種を送り込まれ、徐々に膨れ上がっていくようにさえ感じていた。僕は快感に加えて、倒錯した妄想にすっかり囚われていた……今日一日で僕は浮浪者達のオンナになり、野良犬のメスにさえされた……ああ、こんなにいっぱい彼らの精子が僕の中に植えつけられて……僕はひょっとしたら……。
「ああっ……ああんっ……」
気がつけば僕はまた射精していた……もはやほとんど透明で少量しか出てこない。
ウォン……バウッ。
そのとき犬も高く鳴いた。いつのまにか彼はもがくのをピタリとやめ……同時に結合している部分の違和感に僕は気づく。
「おおっ、始まったみたいやな……」
食い入るように僕と犬の交尾に見入っていた、訛りのある浮浪者が、息がかかるほど僕の尻に顔を近づける。
「ああっ、うそっ……うそっ……だめっ……千切れるっ!」
犬の性器の根元が、僕の肛門の内側で、瘤状に膨れ上がっていたのだ。咄嗟に犬の交尾について僕は思い出す。行為中、雌が逃げないように雄の性器はこうなるのだと、どこかで聞いた。つまり僕を逃がさないために、彼は性器で僕をしっかりと引き止めている……そういうことだ。
「これで兄ちゃんは、すっかりこの犬の雌だな……腹ん中で何億もの精子が元気よく泳ぎまわってるぜ……しっかり元気な子犬生まねえとなあ」
そういって最初に僕にフェラチオを強要した浮浪者が、犬とがっちりつながっている尻を強く叩く。直後に浮浪者達は大きく笑い声を立てた。
軽いゴミが落ちてくる感覚を頬に受ける。
「あ……」
続いて、馴染み深い煙草の匂いに気がついた。いつになく重い瞼を無理やり押し上げると、絵になりすぎる男の顔と目が合った……その表情が、見たこともないほど痛々しく……いや、痛々しいものを見ているような、労わるようなものに見えた。そんな馬鹿な……ありえないと……そう僕は思って、働かない頭で混乱する。そう考えた途端、整いすぎた顔から表情が消えた。
「会社のお荷物の次はホームレスの性奴隷……いや雌犬ですか? ひどい匂いですよ」
言われた言葉にショックを受けた。僕に何が起きたのか……僕がどうなっていたのかを彼……狼森は知っていたのだ。どこから見ていた……見られていた……? 浮浪者に輪姦され、尻を振り、喘ぎ声を上げ、あろうことか犬と獣姦さえして歓喜し……最悪だった。
「放っ……」
放っておいてほしい、そう言い掛けて、自分の体制に初めて気づいた。
僕がいたのは最初に横になっていた遊歩道のベンチだ。そこに同じように身体を横たえ、但し頭の下には暖かい弾力のあるものが当たり、上から狼森が僕を覗き込んでいる……僕は狼森に膝枕をされていた。
「わ……な、何っ……?」
次の瞬間、身体が宙に浮いた。狼森が背中と膝下の手を差し入れて、僕を横抱きに持ち上げたのだ。
「帰りますよ」
そういって彼は僕を抱えて暗い道を進んでいく。森閑とした国立公園の遊歩道は、狼森が歩くたびに靴の下で立てる砂利の音と、微かな夜風が木々を揺らす音だけがいつまでも響く。4月の夜風はまだまだ寒い。なのに狼森が早くもドレスシャツ1枚で歩いていることに気づき、遅れて自分の身体に、自分のものではない、仕立ての良い紺色のジャケットが掛けられていると気がついてしまう……狼森は、確実に僕を守ってくれようとしていたのだ。
遊歩道を出てすぐにやってきたタクシーに乗せられる。狼森も続いてシートへ座り、自分の家ではない行き先を運転手に告げた……狼森のマンションだった。
05
『短編・読切2』へ戻る